選手のケアやリハビリを行う際に、可動域を広げるときによくアプローチするところがあります。
それはスカーティッシュ(瘢痕組織)です。
関節の動きを制限している大きな原因の一つです。
簡単に言うと、炎症の後にできる組織で、関節が正常に動くのを妨げる原因になるものです。
これを取ってあげると、関節可動域は広がります。
ロサンゼルスで活動されている清水さんという方がいらっしゃるのですが、その方がいろんな選手の治療をしていく中で、痛みや可動域制限の原因を突き止めていったときに、このスカーティッシュにたどり着いたそうです。
何度か治療しているところを見学させていただきましたが、治療後の可動域の拡大には目を疑うほどでした。
その治療は手技がメインで骨や関節周り、筋肉と筋肉の間に固まっているスカーティッシュを取り除いていくのですが、結構強い力でアプローチしていきます。
治療を受けている人もだいたい痛そうです(^-^;
しかし、治療後の可動域の拡大に治療を受けた本人も見ている私も目を疑うほどでした。
正直、衝撃でした。
今まで、痛みをなるべく引き起こさないことがケアの基本、という自分の中の常識が覆された瞬間です。
私の解釈では、ベースはモビライゼーションで骨や関節を動かすのですが、その動きを邪魔しているものを手でアプローチして、取り除いて動きを出すことで可動域を劇的に改善しています。
私も清水さんに教えてもらい、見よう見まねで実践したところ、私でも可動域を拡大することができたのです。
今まで私が限界だと思っていた枠を取っ払ってくれるような出来事でした。
そこから、関節可動域を改善しながら、同時に本来動くべき関節が動くことによって、生じていた痛みも改善することができるようになってきました。
もちろん今でもどうにもならないケースはありますが、多くの場合可動域を広げることができるようになりました。
私のこの経験を皆さんにもシェアしたいと思っています。
すべてがスカーティッシュで解決できるとは思いませんが、これまでの経験ではおよそ半数はこのスカーティッシュが原因で関節可動域が狭まり、関節本来の動きができずに、痛みにつながっているケースが意外と多いです。
関節本来の動きを取り戻し、その人のノーマルな動きを再教育し、さらに入力を変えてあげることで、また同じような症状が出ないようにアプローチすることが重要です。
この入力を変えるというところは、これから勉強していきたいところなので、これも新たな知識や技術を習得できればシェアしていきたいと思います。
理学療法士やトレーナーの方のお役に少しでも立てれれば光栄です。


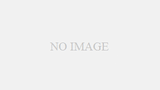
コメント
突然失礼します。
鍼灸師1年目のトレーナーを目指している者です。
スカーティッシュについて気になる為コメント失礼いたします。
スカーティッシュを実際に見つけるには、どの様に評価しているのでしょうか?
私も肉離れの既往がある選手のマッサージをしていて、選手が実際に気にしている部位にしこりの様なザラツキ?の様なものをマッサージしている最中に見つけました。
この様に、選手の主訴と触診をしていく中で見つけているのでしょうか。
視診などからもわかるものなのでしょうか?
また手技がメインと言うことですが、強めの指圧をするということでしょうか。
私はカッピングと指圧でスカーティッシュの様なザラツキの部位にアプローチしたのですが、どの様に治療を行っているのか教えて頂けると幸いです。
長文失礼いたしました。
コメントありがとうございます。
ご質問のスカーティッシュの評価方法ですが、仰る通り選手の主訴と触診が主な評価方法です。
あとは、ストレッチしたときの症状や関節周りであれば関節運動させたときの反応(これは視診になりますね^-^;)など見ます。
あとは実際にアプローチして可動域や症状が改善するかどうか、ビフォーアフターで評価することが多いですね。
アプローチ方法は手技がメインです。
ただ押すというわけではなく、骨や関節の近くであれば、骨にスカーティッシュが付着していることが多いので、ゆっくり押しながら動かして骨から剥がすイメージです。
筋肉の場合は筋と筋の間でスカーティッシュがそれぞれ分離した収縮を阻害していることが多いので、筋と筋を引き離すイメージでアプローチしています。
あとは実際に触った時の感覚が一番重要かもしれません。
これはなかなか文章でお伝えするのは難しいですが(>_<)